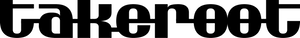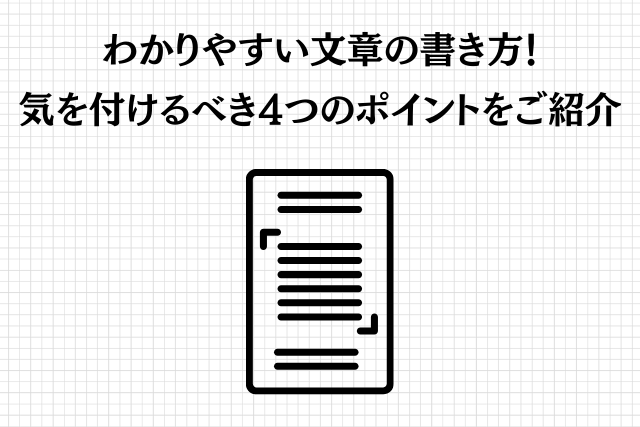皆さんが文章を書くときに、特に注意していることはなんですか?
わたしが文章を書くときに一番気を付けているのは、わかりやすい文章かどうかです。
基本的に記事を書くときには伝えたい内容があります。
「このお店はこんなに素晴らしい取り組みをしている」「この人たちはなんて熱い想いをもっているんだ」こうした内容を伝えたいのに、文章がわかりにくくて伝わらないことほど悲しいことはありません。
ですから、「わかりやすさ」は常に意識しています。
今回はわかりやすい文章を書くために、普段気を付けていることを紹介していこうと思います。
自分の言葉に落とし込んでから書く
別の記事からコピペしてくるのは論外ですが、記事を制作する際に、他の記事を参考にすることはあると思います。
自分があまり詳しくない分野の記事を書かなければならないときだってあるでしょう。
ネット上にはどうしようもない記事も数多く存在しますが、有益な記事だってたくさんあります。
学術論文を書く際にも参考文献が存在するくらいですから、そういった有益な記事を参考にすることはとても重要なことです。
しかし、そこで気を付けてもらいたいのは、きちんと自分の言葉に落とし込んでから書くということです。
自分がその内容をよく理解してもいないのに、この記事でこう書いてあるのだから、きっとあっているんだろう。と、言葉尻だけを少し変えてほぼ同じ内容を書くことはありませんか?
読者はそういった部分を敏感に感じ取ります。
あれ?ここだけちょっとわかりにくいな。なんとなく文体が違う気がするな。という違和感のある、わかりにくい文章になってしまいます。
そもそも自分が理解していないのに、わかりやすく伝えることはできません。
参考にした記事の内容が難しければ、理解できる内容のものを探しましょう。どうにかして理解して、よりわかりやすい言葉に変えて文章をつくってください。
そうすれば、わかりやすいだけでなくオリジナリティのある記事にもなるはずです。
参考にする記事を探してもあまりよい記事が見つからないときもありますよね?
そんなときは、これからは自分の記事をみんなが参考にしたくなるようにわかりやすく書いてやろう!くらいの気持ちで挑んでみてはいかがでしょうか。
必ず声に出して読む
どんなに時間のないときでも必ずやっているのが、書き終わった文章を声に出して読むことです。
これによって誤字脱字に気が付くこともできますし、読みにくいポイントを発見することもできます。
例えば、二つ上の行で似たような表現をつかっているな。とか、語尾が被っているな。とか、リズムが悪いな。といった読みにくいポイントは、一行一行に集中しながらキーボードをたたいているときには気づきにくいものです。
良い文章は音読したときにスラスラとリズムよく読むことができます。
そういう文章は5,000字だろうが10,000字だろうが、読み終わったときにあまり疲れません。逆にリズムが悪かったり、語尾の被りが気になったりしていると文章に集中できませんし、短い文章でも読後の疲労感が大きいものです。
きちんと最後まで読んでもらうためにも、記事の下書きが完成した際には一通り自分で声に出して読んでみてください。
きっと執筆中には気づかなかった読みにくいポイントをいくつか発見できるはずです。
修飾語と被修飾語はなるべく近づける
修飾語とは、単語をより詳しくする言葉のことです。
たとえば、「リンゴ」よりも「真っ赤なリンゴ」の方がどんなリンゴなのかがわかりやすくなりますよね。
「歩く」よりも「とぼとぼ歩く」の方がどんな風に歩いているのかがより鮮明に浮かびますね。
この「真っ赤な」や「とぼとぼ」が修飾語です。逆に修飾される側、今回だったら「リンゴ」や「歩く」が被修飾語です。
この二つは近い方がわかりやすいのですが、油断しているとどんどん離れていってしまうのです。
例を挙げてみましょう。
- 「僕はあの日の出来事を少しずつ思い出した」
- 「僕は少しずつあの日の出来事を思い出した」
- 「少しずつ僕はあの日の出来事を思い出した」
この3つの文は、「少しずつ」という言葉の位置をずらしたものです。
「少しずつ」という言葉は「思い出した」を修飾しているので、最初の文が一番わかりやすいと思うのですが、どれも文としては成り立っています。
成り立っているからこそ、気づかずに書いてしまうのでしょう。
この例は、文自体が短いので、どれもそれほどわかりにくくはありませんが、これが長い文になると特に注意が必要です。
長い文章で修飾語と被修飾語とを話してしまうと、どの言葉がどの言葉を修飾しているのかがややこしくなるのです。
意図をもって離すという場合はかまいませんが、特に考えずに修飾語と被修飾語を話してしまうのはあまりおすすめしません。
一文はできるだけ短く
先ほどの話とも少し被るのですが、一文が長くなりすぎてしまうと読みにくい文章になります。
もちろん短すぎても味気なく感じてしまうので、程よい短さを心がけましょう。読点(、)が5つも6つもついていたら要注意です。
読点のつけ方も少し注意が必要で、全然つけないと読みにくくなりますし、あまりつけすぎると気になって読みにくくなります。
これも声に出して読んでみることで解決するかもしれませんね。
まとめ
何かを伝えたくて文章を書く以上、読みやすさという点をないがしろにしてはいけません。
後半に書いた修飾語と被修飾語をなるべく近づけることや、一文の長さ、読点の数など、テクニック的な部分も大切ですが、何よりも最初の2つが重要だと思います。
自分の言葉に落とし込んで書く。書き終えた文章は必ず一周か二周は声に出して読む、ということはぜひ実践してみてください。
どんなに時間がなくてもこの二つを徹底することで、記事のクオリティ、読みやすさは向上すると思います。