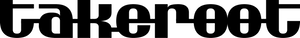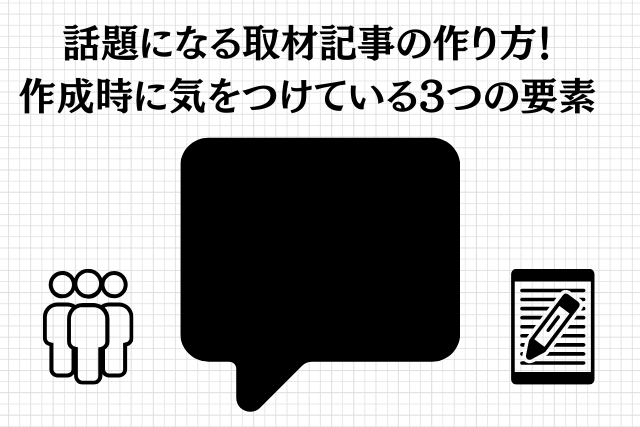皆さんは自分の書いた取材記事がバズった(話題になる)ことはありますか?
わたしは何度かバズった経験があります。
例えばこちらの記事。

記事:デマに惑わされるな!色々と話題の「レゴランド」に行ってきたから、とりあえず聞いてくれ
名古屋にレゴランドがオープンした際に、ネットで流れていた悪評が本当なのかを検証しにいった記事なのですが、twiiterから火が付き、かなりバズりました。

現在はサーバー移行の関係で記事内での数字はリセットされているのですが、当時は828ブクマされ、50万PVくらい読まれていました。
レゴランドほどではありませんが、こちらの記事もバズっています。

記事:西成区は「やばい」って本当?現役教員と元住民に案内してもらってきた
こちらの記事は、関西では治安が悪いと噂されることの多い大阪市の西成区を、西成区で現役教員をしている方と元住人に案内してもらった記事です。
2017年に書いた記事なのですが、今でもずっと読まれ続けている記事となります。
わたしは「バズった記事=良い記事」だとは思っていません。
記事を書く時にもバズりたいという思いよりは、長く読まれ続ける記事が書きたいと思いながら作成しています。
しかし、どうせなら話題になるような記事を作りたいですよね。
もちろんわたしも自分の書いた記事がバズって話題になるのに越したことはないと思っています。
そこで、自分の中で整理する意味も込めて、話題になる記事の特徴や共通点を考察してみようと思います。
圧倒的に面白い記事をつくることは難しい
まずはどんな記事が話題になっているのか考えてみました。
例えば、オモコロなどで有名なARuFaさんやヨッピーさんが書くような圧倒的に面白い記事が書ければ話題になるでしょう。彼らが記事を更新するごとに必ずと言ってもよい程はてブされ、Twitterでも自然とRTで回ってきます。
しかし、それを狙って書くことはまず無理です。
あんなに面白い記事をみんなが狙って書くことができれば、毎日のように面白記事を読むことができるのでわたしとしては大歓迎なのですが、実際にはまずお目にかかることはありません。
ですから、天才的な企画力、構成力、文章力がある人は別として、わたしたちのような多くの一般人は面白とは別の部分で勝負しなければなりません。
話題になる記事は拡散したくなる記事
面白い企画が思いつかなくても、話題になる記事とはどのようなものでしょうか。
話題になる、バズるということは、拡散したくなるということが大切です。
では拡散したくなる記事とはどのような内容なのか。
わたしが過去にバズった記事から考えてみると共通する3つの要素が出てきました。
広めなくてはいけないという義務感を生み出す内容
たとえば最近TwitterのRTで回ってきたツイートなのですが、ロードバイクに乗っている男性が小さな女の子をひき逃げしたというショッキングな映像が乗せられたものです。
幸いにも女の子は命に別状はなかったようですが、ロードバイクに乗っていた男性はいまだに見つかっておらず、情報提供を呼びかけるものでした。
このツイートはすでに10万RTを超えているのですが、これをRTしている人たちはきっと正義感からだと思います。
女の子がかわいそう。ひき逃げは許せない。
そういった気持から、これを広めなければならない!という義務感に近いものが生まれているのではないでしょうか。
今回の例はツイートでしたが、記事も同様で、読み終わった後に「このことを広げないといけない!」と思ってもらえれば拡散につながるはずです。

レゴランドの記事はまさにそんな内容でした。
レゴランドはオープン前から悪評が流れていて、かなり悪いイメージだったんです。
わたし自身、現地に行くまでは記事の方針を決めていなくて、「ネットでの悪評が嘘だったらきちんと検証しよう。でも実際にダメダメだったらそれを正直に書こう。」と考えていました。
実際にレゴランドに行ってみたら、「確かにこれはちょっとな」と思う部分もあったにはあったんですが、すごく素敵な空間だったんですね。
そして何より現地に行ってもいない人のデマや嘘の情報が目立ったんです。
午前中に現地に行って、もう昼過ぎくらいには記事の方針も固まったので、閉演時間を待たずに急いで帰ってその日の晩のうちに書きあげました。
記事の内容は、デマ情報を一つひとつ訂正して、実際に現地に行かなければ伝わらない雰囲気を伝えるというもの。別にレゴランドの記事広告ではないので、悪かった部分も正直に書きました。
すると公開当日、世間のレゴランドへの興味も手伝って、めちゃめちゃ拡散されました。
拡散してくれた人たちのほとんどは、正しい情報を伝えたい、というものだったと思います。
記事を作成したわたしも同じ気持ちだったので、これは本当にうれしかったですね。
議論を生み出す内容
これも先ほどの内容と少し似ている部分があるのですが、議論を生み出す内容は拡散されやすいと思います。
というのも、SNSで発信する人々の多くは、自分の意見を言いたい、伝えたいという思いがあります。
明らかに片一方が正しく、もう片方が間違っているような内容では、議論にもなりませんが、賛否が分かれるようなものであれば、記事を読んだ後や、他の人の意見を目にした後に「自分も一言言っておきたい」という気持ちになる人も少なくないのではないでしょうか。

西成区の記事はそんな内容だったと思います。
これも実際に行ってみると噂に聞くような怖い場所ではなくて、一日楽しく過ごせたので、それを記事にしました。
さらに現役教員や元住人、西成区で働いている人たちに話を聞くことで以前に比べて変わった部分、これから変わらなければならないことなど、少し社会的な内容でした。
この記事に対して「行ったことなかったのに自分も冗談半分で噂を話していた。反省した。」というような意見もあれば「この記事は西成区の良い部分しか映していない」というような意見もありました。
この記事を作成しているときには議論を生み出してやろうなんてつもりはなかったのですが、結果的にそういった部分も拡散されていった理由の一つだったと思います。
共感できる内容
ロボットは命令で動く、人は共感で動くという言葉があるくらい、人間は共感できるものに対して好意を抱きます。
記事で言えば、より具体的で、より実際に体験した人にしかわからない内容であればあるほど、同じ経験をした人の共感を生み出します。
これはわたしが書いた記事ではありませんが、ライターの前田さんが書いた洗脳研修の記事がまさにこの部分で爆発的に拡散されました。
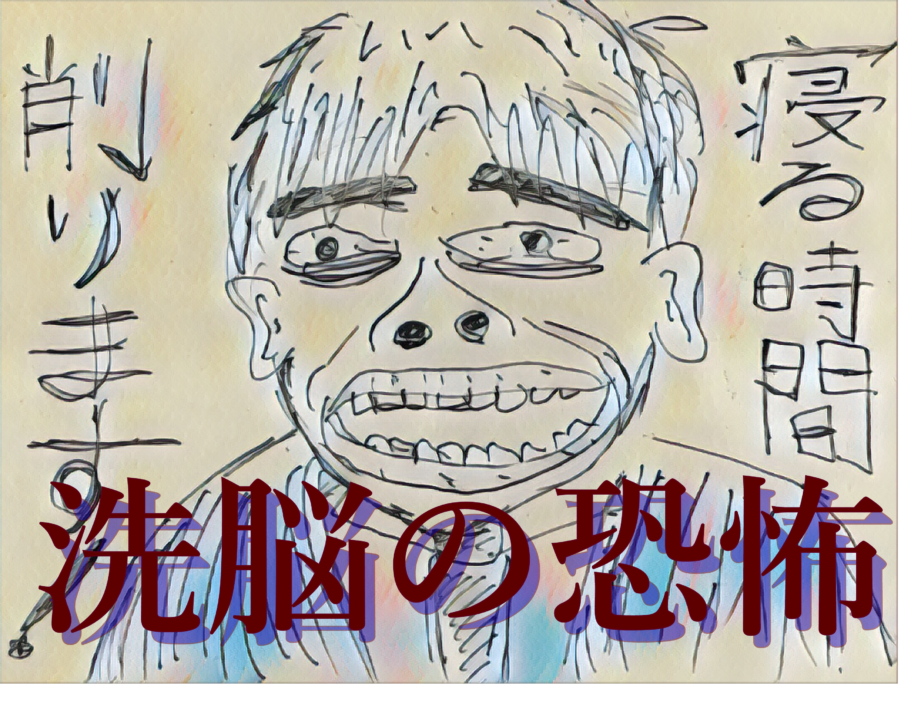
記事:洗脳研修!ゲイビデオ出演疑惑!新卒で入った会社を14日で退社してきた(前編)
これはフィクションのように思われる方もいるかもしれませんが、本当に前田さんがリアルタイムで新卒の会社の研修を受けて書いた記事です。
新人研修に行くと言っていた前田さんからチャットワークで「この会社辞めようと思うんですけど、ロカフレで記事にしてもいいですか?」と送られてきたときには目を疑いました。
しかし彼はその言葉通り、新卒で入社した会社をたった14日で辞めて、この記事が完成したのです。
数日前に実際に体験した前田が書くからこそ文章からにじみ出るリアルさは真に迫るものがあります。
また、こうしたパワハラ的な新人研修は実際に日本中のいたるところでおこなわれていたため、経験者はものすごい共感を得たと思います。
これは前編と後編に分かれているのですが、二つ合わせて1900ブクマされ、ロカフレ史上1番バズった記事となります。
まとめ
話題になる記事は、それを読んだ人が拡散したいと思う内容です。
- 義務感を生み出す内容
- 議論を生み出す内容
- 共感できる内容
これはあくまでも例にすぎませんが、過去にバズっている記事はこの3つの要素のうち、2つか3つ全てを持っているものでした。
最初にも言いましたが、バズった記事=良い記事だとは思いません。
例えば炎上狙いで話題になっても、その記事に本当に価値があるとは思えないですよね。
長く読まれ続け、なおかつ話題にもなる記事を書く。
これは難しいことですが、上で挙げた3つを少し意識しながら記事を作成することで、少し話題になりやすくなるのではないでしょうか。